【CASE1】
共に創業したが、今は事情の異なる3兄妹⇒会社も活かして兄妹仲良く別の会社を経営
血のつながった兄妹が同じ会社を経営する……何だか、テレビドラマの設定のようで、素敵な、ロマンチックな話に聞こえます。
しかし、血のつながった兄妹だからこそ、いったん話がこじれた場合、経済的な事情だけではない葛藤が生まれやすくもなります。
そんな時、第三者がどうコーディネートしていけば全員が納得し、会社も順調に経営を続けていけるのでしょうか?
健康食品のネット通販。順調に成長中。

長男:東京誠一
(共同創業者、ただし別の企業も経営)

次男:浩次
(共同創業者、ただし別の企業も経営)
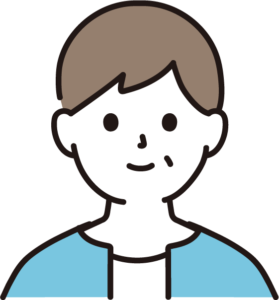
末妹:彩華
(社長、当初出資はせずに創業時から実務を担当)
「すごい健康通販株式会社」は、健康食品を中心とした商品を、インターネットで販売している家族経営の企業です。
当初、この会社を設立したのは、長男の誠一氏、そして次男の浩次氏でした。
資本金は600万円。
末っ子の彩華氏は資本を出していません。
設立当時の資本構成

長男:誠一氏
400株(66.7%)

次男:浩次氏
200株(33.3%)
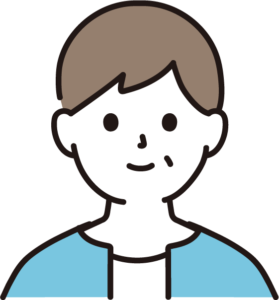
末妹:彩華社長
0株
兄妹での共同経営ではありますが、資本上は誠一氏がオーナー経営者、支配株主であり、浩次氏は少数株主、彩華社長は持ち株なし。
肩書では、誠一氏が代表取締役社長、浩次氏は取締役、実務を担当する彩華社長は当初、一従業員の立場でした。
一方で、誠一氏、浩次氏は当社以外に別の企業も共同経営しており、そちらが忙しかったこともあって、実務に慣れてきた彩華社長に任せ、徐々に経営にはタッチしなくなり、やがてほぼ「丸投げ」に近い形になっていました。
彩華社長は取締役、ついで株主である2人の兄によって代表取締役社長に選出されました。
経営は初めてでしたが、思わぬ才能を発揮していきます。
もともと自分自身、健康食品への関心が高く、顧客のニーズや最新の流行を捉えるのが得意で、いち早く大量の仕入れを行うことで原価率を下げ、定期購入の顧客を多数確保して、競争力を強化します。
さらにCRM(顧客関係管理)を導入して顧客の動向を分析し、「あわせ買い」「ついで買い」のきっかけを上手につくり、新しい売れ筋商品の開発にも複数成功して、客単価を引き上げていきました。
ある時期からインターネット広告も出稿し始め、事業規模は急成長していきました。
兄2人は別会社の経営にかかりきりで、また、株式や不動産の投資も行っていましたから、「すごい健康通販株式会社」の現状にはあまり関心を持っていませんでした。
というより、順調な経営が行われていること、ほぼノータッチなのにある程度まとまった役員報酬が入ってくること、そして何より血を分けた妹に任せているのだから、任せきりでいいだろうという考えだったのです。
経営者として頭角を現し始めた彩華社長には、やがて同じようなビジネスを展開している女性経営者の友人ができました。
彼女は彩華社長の手腕と、置かれている状況を考えれば、株を一切持っていないのはもったいないし、一部でも株を持っているほうがいっそう励みになるとアドバイスしてくれました。
そこで彩華社長が税理士に相談すると、やはり頑張った分だけ将来株価の上昇が期待できるのだから、可能
であれば株を持っていたほうがいいと言われたため、ひとまず長兄の誠一氏に相談を持ちかけ、持ち株のうち200株を、額面のとおり200万円で買い取ることにしました。
この時点での株式保有率

長男:誠一氏
200株(33.3%)

次男:浩次氏
200株(33.3%)
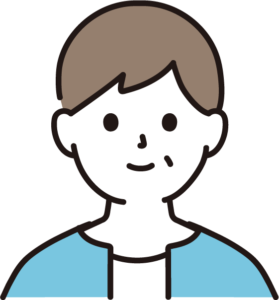
末妹:彩華社長
200株(33.3%)
これで、3兄妹・3取締役がまったく同じ保有率となりました。
多忙で関心がなく、取締役会や株主総会まで丸投げしていた兄2人でしたが、ある時、彩華社長がどのくらいの報酬を取っているのかを偶然知ってしまい、がくぜんとします。
誠一氏が年380万円、浩次氏が120万円なのに対して、彩華社長は5300万円の役員報酬を受け取っていたのです。
ほぼ何もせずに報酬だけを受け取っていた2人でしたが、この数字を見て、怒髪天を突くかのごとく気分を害してしまいました。
彩華社長の役員報酬は、誠一氏や浩次氏が他の会社から得ている報酬を足した額よりも、断然高かったからです。
相談もなく高い年俸を得ていたことへの怒りとともに、ひそかに「兄貴」として、経営者の先輩としてのプライドも傷つきました。
しかし考えてみれば、あまり大きな口を叩ける立場でもありません。
そもそも、そこまで高額の役員報酬を受け取れるほどの高収益企業に変貌していたことも知らなかったわけです。
もともと株主なのですから、その気さえあればいくらでも経営に口は出せたはずなのに、丸投げを続けていたのもまた自分自身ですし、会社をここまで成長させたのは全面的に彩華社長の功績です。
そこで兄2人は、今後たもとを分かち、彩華社長単独で経営していくこと、そしてしかるべき金額で兄2人の株式を買い取ることを要求しました。
彩華社長は、税理士と相談の上、簿価純資産方式で算出した1株50万円での買い取りを回答しました。
1人につき、200株×50万円=1億円の評価となるわけですから、一見悪い条件には見えませんでした。
ところが、兄2人が税理士と相談すると、株式の発行会社が自社株を買い取る場合はみなし配当扱い(配当以外の行為に対しても税務上は配当と同じとみなして課税を行うこと)になるため、分離課税ではなく総合課税となり、取得原価、すなわち発行当時の額面が200株=200万円なので、利益は1億円-200万円=9800万円、そこに所得税45.945%と住民税10%の計55.945%(約5,482万円)が課税され、手元には4518万円(9800万円-5482万円+200万円)しか残らないことが判明し、ショックを受けます。
3兄妹間の経営権譲渡の話の出口を模索している頃、彩華社長から知人を通じて私のところに相談が持ち込まれました。
守秘義務契約を締結した上で財務データを拝見、事業内容もリサーチして、どうにか兄妹3名が仲良く、円満に解決する道がないか、模索を始めました。
「すごい健康通販株式会社」損益と資産の状況
| 売上 | 10億円 |
| 売上総利益(粗利)率 | 60%(6億円) |
| 営業利益 | 1.2億円 |
| 経常利益 | 1.2億円 |
| 税金 | 0.5億円 |
| 税引後当期利益 | 1億円 |
| 現預金 | 4億円 |
| 長期借入金 | 1.4億円 |
| 純資産 | 3.1億円 |
| 総資産 | 5.8億円 |
| 自己資本比率 | 53.4% |
損益の状況は、会社の規模を考えれば、非常に立派な高収益企業という印象です。
次に、資産の状況は、手元流動性もあり、自己資本比率も高く、彩華社長は文句なしの優秀な経営者と言えます。
まして、5300万円もの高額報酬を受け取りながらこれだけの利益を残しているのです。
私のような第三者からは、思わず「あっぱれ!」と声が出るレベルです。
ただ、ここまでの経緯から、兄2人と彩華社長との間では解決策のアイデアがなく、お互いに苦慮している状況だったため、まずは兄2人が納得できる株価で、私たちが株式を取得することを提案し、株主名簿の書き換えを行った後で、彩華社長に対して相談することとしました。
それは、我々が3分の2の大株主として、経営コンサルタントの知見でアドバイスするものの実務は彩華社長に全面的に委任する案と、我々の株式は彩華社長に買い取ってもらい、100%オーナー社長となる案です。
その後、最終的に彩華社長が納得できる株価で買取っていただくことになりました。
そして共にビジネスを始めた3兄妹が、仲良くお互いのビジネスに専念できるスキームを考えました。
それは、彩華社長が引き続き会社を運営するために必要な運転資金を手元流動性で確保しながら、私たちが取得した残りの400株を自社株式として取得することにより、100%の経営権を確保することです。
彩華社長も大きく負担を増やさず全株を集約し、実力に見合う形で、完全なオーナー経営者になることができました。今後も新鮮な発想のもとで成長を続けるに違いありません。
【CASE1 まとめ】
このケースを解決する際のポイントは、
でした。
私たちのソリューションで、3名が納得できる形で経営権が譲渡されました。
それぞれ今後も新たな気持ちで経営に邁進されることでしょう。
【CASE2】
「終活」で株を手放したい少数株主の叔父・叔母と、経営不振で買い取りに高値はつけられない三代目⇒複雑な親族関係を円満解決
祖父の起こした会社を継いでどうにか看板を守っている三代目。
甥っ子の三代目を支えてきたもののもう高齢の叔父と、経営に関わってこなかった叔母。
決して高収益でもない製造業での株の買い取りをどうすべきなのか、誰も身動きが取れない……こうした、日本のあちらこちらにあるオーナー経営者の悩みを交通整理するには?
精密部品の製造。1935年から三代続いている長寿企業。
- 祖父……田中太郎(創業者、他界)
- 父………栄一(二代目、太郎の長男、他界)
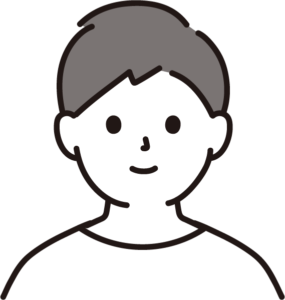
本人:栄太郎
(三代目現社長、栄一の長男)

親族:幸雄
(太郎の次男、存命)

親族:久恵
(太郎の長女、存命)
「福岡精密株式会社」は、1935(昭和10)年創業の精密部品製造業で、いわば「米寿企業」です。
経営は代替わりを経て現在三代目の栄太郎氏。
この間、創業者一族が株式を分け合って保有し、互いに役員を務めてきた、典型的な同族企業です。
会社は一般的な「町工場」ですが、長年の信用と技術力を背景に優良企業との取引をかかえていて、順調と言えなくはない状況でした。
ただ、近年の世界情勢による原材料高、さらに発注元からの値下げ要請が続いており、収支のバランスが保てず、切り崩しでしのいでいる状況です。
創業者の太郎氏(故人)、現経営者の父である二代目の栄一氏(同)の時代までは素晴らしい業績を出していて、当時からの内部留保をどうにか保ってきました。
ただ、このままでは先行きが不安にならざるを得ません。
そんな中、栄太郎社長のもとに、叔父、つまり父の弟に当たる幸雄氏から、株式を買い取って欲しいという依頼が続いていました。
幸雄氏は、かつて専務取締役として兄の二代目を支え、三代目の経営継承を見守ってきた人物です。
現在は66歳となり、すでに引退していて、役員でもありません。
幸雄氏の2歳下の妹、つまり栄太郎社長の叔母である久恵氏も、事情こそ違うものの、兄の幸雄氏が株式を売るのなら、その機会に自分の持分もいっしょに売却したいと考えています。
というのも、久恵氏は経営にも事業にも関与してこなかったため、もともと株の保有に関心がなかったからです。
株を買って欲しい親戚2名からの継続的な要求、そして経営の先行き不透明で、栄太郎社長は悩んでいました。
経営権集約という意味では、魅力的な話でもあります。
相続や譲渡の結果、現時点での持ち株の状況
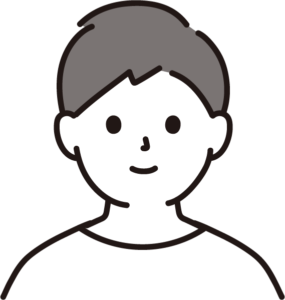
栄太郎氏(現社長)
15%

栄太郎氏の長姉
15%

栄太郎氏の次姉
15%

幸雄氏+2人の子
22.5%

久恵氏+2人の子
22.5%
栄太郎氏の2人の姉はいずれも他家に嫁いでいて、経営に関与していません。
この親族、基本的に関係は良好で、あまり大きなトラブルはありません。
しかし、そろそろ体力の限界を感じ、「終活」を望んで、可能ならば現金化したいと考えている幸雄氏の一家、幸雄家がそうするならぜひこの機会にも自分も処分したいと考えた久恵氏一家の買い取り希望に対して、直近の経営が厳しくキャッシュアウトを嫌う栄太郎社長は、否定的な反応を示しながらも決定的に断るわけにも行かず、のらりくらりと反応してきました。
近年の業績が振るわないだけではありません。
自分自身は15%しか株をしておらず、見かけ上は少数株主ですが、経営に関わっていない2人の姉の株は自分が任されているも同然なので、事実上全体の45%は確保しています。
では、過半数越え、あるいは3分の2を超えて保有する機会を逃すべきではないかというと、その点も正直ピンときません。
引退した幸雄氏、一切経営に関心がない久恵氏の2家の保有率を合わせると55%となり、経営権を握れることになりますが、もともと彼らは栄太郎氏の経営を脅かす存在ではなく、あくまで「仲のいい親戚のおじさん、おばさん一家」だからです。
これは反対に、栄太郎氏から見れば、わざわざお金を出してまで、株を買い取り経営権を確実に保有するモチベーション自体が薄いことになります。
強気には出られない幸雄ファミリー、久恵ファミリーでしたが、お互い病気気味ということもあって、会えば体の不調の話ばかり、この先いつまで元気でいられるか自信が持てません。
さらに相続が発生すると、自分の子どもが複雑な状況で株式を引き継がなければならなくなります。
2人で話し合った結果、ついに途方に暮れている心境を栄太郎社長に吐露しました。
かといって、栄太郎社長にも妙案は浮かびません。
この状況をどう打開すればいいのか、それはつまり、会社の現状を踏まえ、みんなが納得できる株の売買価格を算出することにほかなりません。
こうして栄太郎社長から私たちに相談が持ち込まれました。
そこで守秘義務契約を締結の上、財務データと事業内容のリサーチを始めました。
「福岡精密株式会社」損益と資産の状況
| 売上 | 263百万円 |
| 営業損失 | 24百万円 |
| 経常損失 | 11百万円 |
| 税引後当期純損失 | 12百万円 |
| 現預金 | 88百万円 |
| 総資産 | 283百万円 |
| 純資産 | 202百万円 |
| 自己資本比率 | 77.7% |
まず損益は、決して楽観できるものではないことがうかがえます。
反面、資産のほうは、立派な数字になっていました。
総合すれば、過去からの蓄積は素晴らしいものがありながら、最近非常に苦労していて、取り崩している様子が見て取れます。
栄太郎社長がキャッシュアウトを嫌う理由がよく理解できますし、この会社に限らず、株の買い取りの話がなかなかまとまらない理由としては、よくあるパターンでもあります。
そこで私たちは、現経営者である栄太郎氏の納得できる株価での買い取りによる経営権の確保と、幸雄ファミリー・久恵ファミリーが納得できる株式価値での現金化を解く「連立方程式」を編み出すソリューションを模索しました。
まず、栄太郎社長と2ファミリーが、このまま微妙な空気となり、いがみあう事態は避けなければいけません。
何よりも草葉の陰で二代目の太郎氏が悲しむでしょうし、彼ら自体も望んでいないからです。
同時に、もしも栄太郎社長が安定した経営権を確保できるのなら、それはオーナー経営者として根本的な重要事項とも言えます。
言い方を変えれば、このままの事態を放置していると、将来第三者に経営権を乗っ取られるリスクがないとは言いきれないからです。
これまでの話し合いで、栄太郎社長と2ファミリーでは取引が成立する可能性がうすいため、まずは私たちが2ファミリーと交渉し、株式価値の計算結果をご覧いただいた上で、納得いただける価格で買い取ることに成功しました。
この時点で心の荷物が整理できた幸雄氏、久恵氏からは、残りの人生を楽しむ資金が手に入ったことも併せて、大変感謝されました。
当社が保有した株式は、発行会社である福岡精密において名義をいったん書き換えたうえで、栄太郎社長の指名する代理人とやはり株式価値の計算結果をもとに交渉を進め、円満かつ友好的に買い取り価格を決めることができました。
これで栄太郎社長は、単独で70%の株式を所有することになり、名実ともにオーナー経営者となったわけです。
今後は、残された経営リソースを最大化して、世界的な環境変化、技術革新の難局を乗り越えていただきたいと願うばかりです。
【CASE2 まとめ】
このケースを解決する際のポイントは、
でした。
今後も仲の良い親戚関係を保ちながら、相続の心配なく余生を楽しんだり、経営権の心配なく新しい道を切り開くそれぞれの人生を探って行かれることを祈ります。

